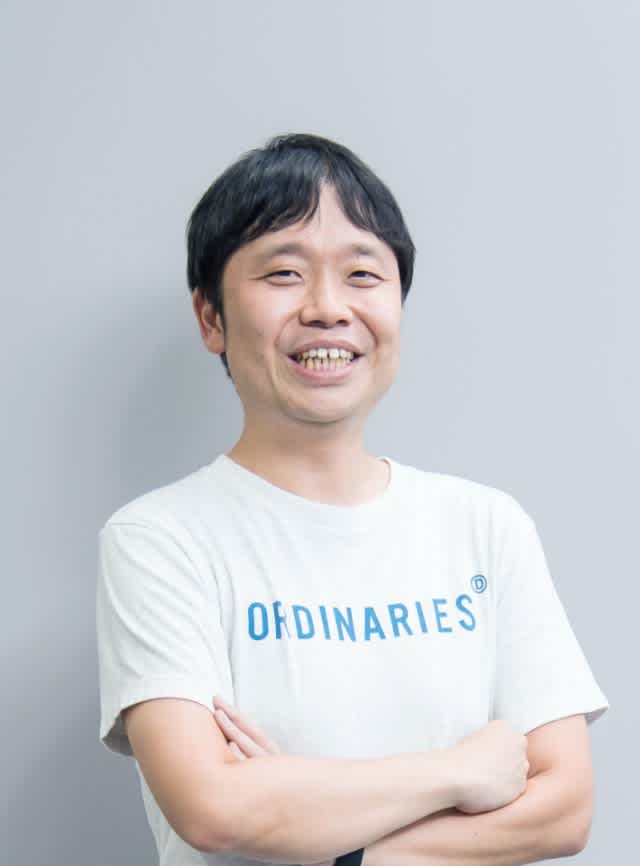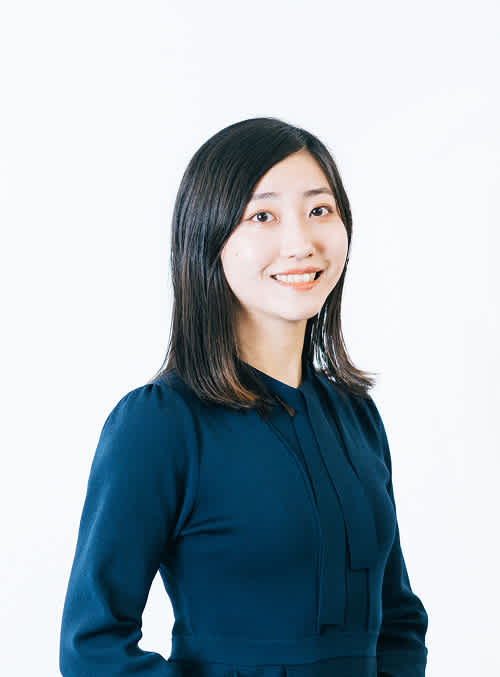Staff interview
#47

01. 担当者プロフィール

担当者プロフィール
- お名前:上原 悠希 / Yuki Uehara
- 組織名:コンテンツマネジメント部
- 入社時期:2021年 10月

担当者プロフィール
- お名前:早川 豪人 / Hideto Hayakawa
- 組織名:コンテンツマネジメント部
- 入社時期:2022年 03月

担当者プロフィール
- お名前:向後 祥子 / Sachiko Kogo
- 組織名:コンテンツマネジメント部
- 入社時期:2022年 10月
2012年に『スタディサプリ』の前身である『受験サプリ』が誕生して以来、10年超。この間に社会はコロナ禍やテクノロジーの進化を経験し、高校生の学習環境も変化しています。そうした時代にあわせたコンテンツ制作を実現するために、制作体制の大規模な見直し・適正化を行ったのが「高校コンテンツ制作適正化チーム」です。この取り組みはどのように実現できたのでしょうか。プロジェクトを推進した、上原悠希さん、早川豪人さん、向後祥子さんにこれまでの道のりやこだわりを聞きました。

02. 「今のやり方が本当にベストなのか」。メンバーの声を起点にプロジェクトが発足
Q:まずはこれまでの経歴をご紹介ください。
上原:私は『スタディサプリ』以前から教育系のコンテンツ編集の仕事でキャリアを積んできました。1社目では通信教育の教材を扱っていて、2社目では教科書編集を担当。毎月発行するために効率性が重視されていた通信教材と、時間をかけて検討に検討を重ねていた教科書で、仕事のスタイルは両極端でした。出産を機に自分のキャリアを考え直し、次は両者の良い面に関われる環境を選び、2021年にリクルートへ転職。入社以来、社会・英語・国語などの文系教科のコンテンツ制作に携わっています。
早川:私も前職では教育系出版社に勤めており、そこでは高校の生物を担当。新学習指導要領に則って教科書を刷新するタイミングでは、教科書にQRコー�ドを掲載して授業動画を参照できるコンテンツを企画・制作。紙とデジタル教材の融合にも挑戦しました。そうした経験から、これからはデータやデジタルを活用した教育の時代の到来を確信。自分自身の新たなチャレンジとしてこの分野の企業に飛び込んでみようと、リクルートに転職してきました。現在も教科としては引き続き高校の生物を担当。加えて、日々の授業で学んだ知識・技能が身についているかを確認する「到達度テスト」の媒体リーダーも務めています。
向後:私も転職以前から教育系の教材編集をしていました。英語を担当し、一通りの業務経験を積むことができた一方で、前職は難関大を志望している生徒向けの教材を出版していたので、届けられる対象が限定的だった。より多くの人に教材を届ける仕事がしたいと考え、『スタディサプリ』を提供しているリクルートを次のキャリアに選びました。担当教科は引き続き英語。通常の講座や学校向け教材の開発に携わっています。
Q:みなさんが取り組んだ、「高校生向けのコンテンツ制作適正化」とはどのようなプロジェクトなのでしょうか。
上原:このプロジェクトは、既存の教材コンテンツ制作フローを見直し、今の時代に最適な形へとアップデートした取り組みです。リクルートの新規事業として『スタディサプリ』が誕生して以来、制作フローはサービスの変更・拡充や事業規模の拡大にあわせて走りながら構築してきた状態。現状でも安定運用は実現していましたが、この10年の間に社会はコロナ禍によって多くの人がオンライン授業を経験。学びのあり方も変化して��います。また、テクノロジーの進化によって、コンテンツ制作の常識も変わろうとしています。
加えて、私たち3人のように他の教育系出版社で編集を経験しているメンバーの視点では、『スタディサプリ』以外のやり方も知っているからこその改善点も感じていたんです。「これって今の方法が本当にベストなのかな?」「でも、もう出来上がっている進め方だから簡単には変えられないよね……」とみんなが漠然と思っていた状態。そんなとき、あるメンバーから「今の時代に合った形へ、ゼロベースで考えてみませんか」と声が上がり、コンテンツグループの思いが一つに。ボトムアップでこのチャレンジは始まっているんです。

03. 10年分のデータやナレッジを紐解き、大胆に手を加えるリスクと覚悟
Q:このプロジェクトでみなさんはそれぞれどのような役割を務めたのですか。
早川:プロジェクト自体はグループのみんなで力を合わせて実現したものです。その中で、上原さんが「テキスト教材制作のフロー整理」、向後さんが「著作権の管理や申請フローの見直し」、そして私が「アセスメント(到達度テスト)まわりのフローの適正化」を担当しています。
Q:では、それぞれのパートで経験したこだわったことやチャレンジしたポイントについて教えてください。
上原:私が担当した制作フローの整理については、歴史も長い分だけ、時代にあわせたもっといい方法があるのでは、と多くの人が漠然と思っている状態でした。そのため、「品質・コストの両面でメリットがあるなら�、取り組んだ方が良い」とフローを変えること自体は、スムーズに合意が得られたんです。ただ、実際にフローを切り替えていく時が思っていた以上に大変でしたね。
というのも、テキスト教材の制作・印刷には膨大なデータが使われており、それは過去10年超の制作実績が蓄積されたものです。旧フローから新フローに移管するにあたっては、一つひとつのデータを紐解いて整理する必要がありました。万が一データに不備が発生して印刷ミスが起きれば、高校生や先生にも迷惑がかかる。社内外の関係者の力を借りながら一件も漏らさず正しくチェックし移管させることにこだわりました。
その際、私たちがチャレンジしたのが新フローへ安全に移行するためのデータ管理方法。私たちは普段、編集者として制作物にミスが出ないようにタスクを細かく分解してチェックすることを徹底しています。そうした品質管理のスキルと発想を、このプロジェクトにも応用しながら乗り越えていきました。
Q:著作権まわりでは、何がポイントになったのでしょうか。
向後:教材コンテンツにおける著作権管理は、一般的なコンテンツと比べて少し事情が異なります。例えば文章問題の一つひとつはその元となる文章の著者から許諾を得て問題を制作しています。コンテンツを一つ作ろうとすればたくさんの人の著作権が絡んでくるのが教材の世界。加えて、英語の問題などは海外の著者にも確認を取らなければならず、海外の権利事情も理解した対応が求められます。
そのため、新フローへの移行によって本来は行われるべき手続きが抜け落ち、申請されないままの利用や許諾範囲を超えた利用が起きてしまうことが最大のリスクでした。そこでフローを変更するにあたっては、これまで暗黙知化していたフローを改めて整理し、担当者に一任していた細かな手順を聞いて内容を確認。適切に移行できるスキームを組み立てつつ、移行後に適切な管理が継続できるような仕組みと体制を社外のパートナーと協働しながらつくっていきました。

04. 課題やビジョンを明文化し、様々な立場の人たちから“理解”以上の“納得”を引き出す
Q:早川さん担当の「到達度テスト」では、何がポイントになりましたか。
早川:「到達度テスト」はアセスメントという性質上、毎年新しくつくるものなので、制作フローを切り替えるにあたっての移行作業のハードルはそこまで高くなかったんです。一方、「到達度テスト」はリクルートの社員だけでなく社外パートナーなども携わっています。また、「到達度テスト」は生徒や先生が今後の学習計画を立てたり、『スタディサプリ』の継続利用への影響が大きかったりと注目度が高く、カスタマーサクセスや営業活動への影響も大きい。様々な人たちが関わっているため、みんなが安心して移行できるような合意形成がポイントになりました。
そこで私が大切にしたのは、コンテンツグループとしての方針��を一方的に共有するのではなく、様々な立場の人と膝を突き合わせて会話をし、懸念点を洗い出して潰していくこと。それぞれの視点からの意見に丁寧に耳を傾けるとともに、“理解”をしてもらう以上の“納得”や“共感”を引き出すことにこだわりました。
Q:三人三様の工夫やこだわりがプロジェクトを推進させていったのですね。取り組みの結果、今はどのような状況なのでしょうか。
上原:大きなトラブルなく、新年度に間に合う形で新フローへの移行が完了しています。ただ、今回私たちが実現したのは、あくまでもコンテンツ制作の基盤を整備したところまで。高校生に価値ある学びを届けるという意味では、この基盤のもとで良質なコンテンツをつくっていくことが必要です。フローの適正化によってコンテンツ制作に関わる人たちに良い変化をもたらし、その先に良いアウトプットがたくさん生まれることが、真の成果だと思っています。
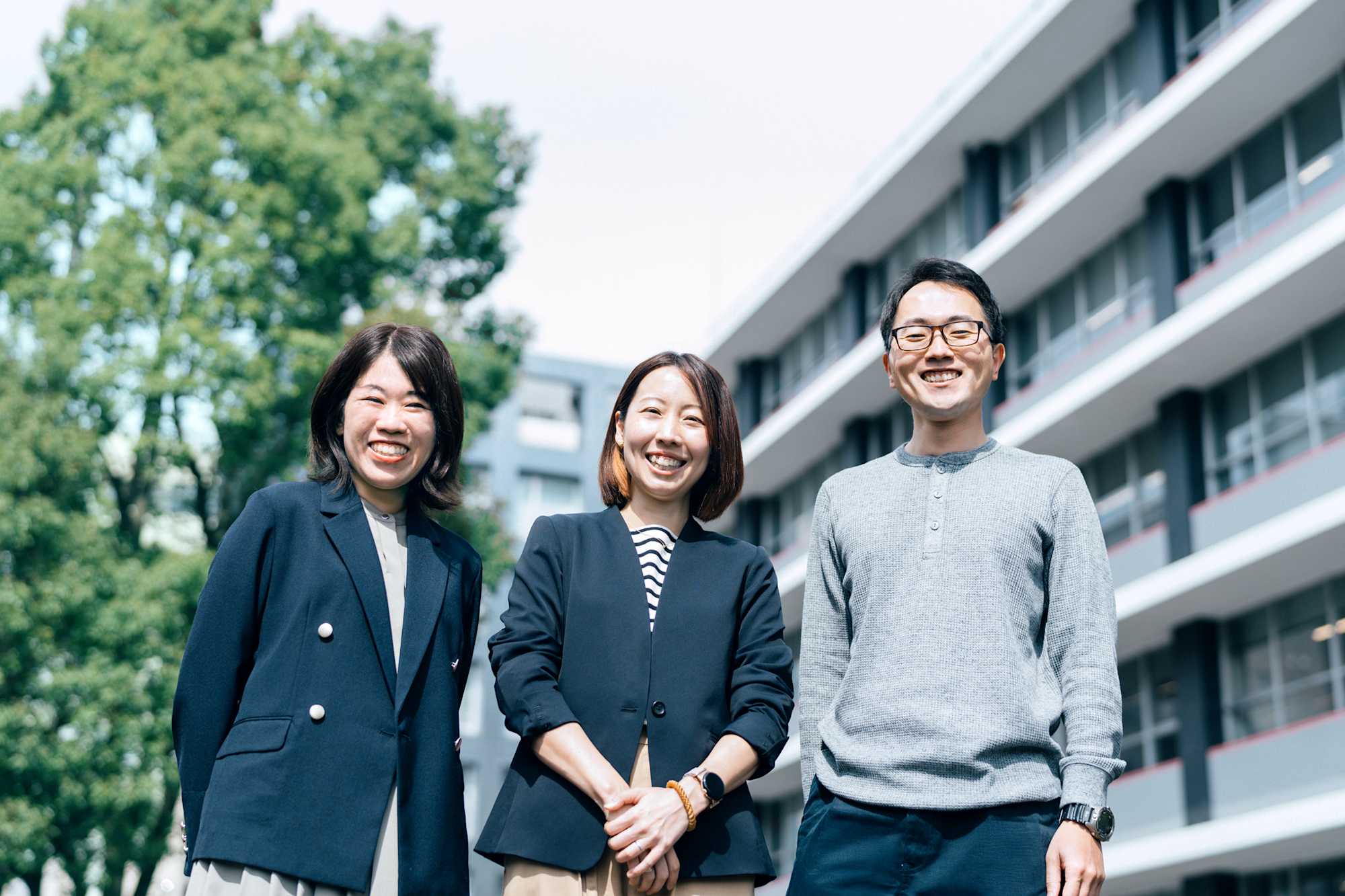
05. 生徒が大人になっても覚えているような、“記憶に残る教材”をつくっていきたい
Q:今回のチャレンジにどのような手応えを感じていますか。
向後:私が従来やってきた編集の仕事は、ひとりでコツコツと進める業務や1対1のコミュニケーションが多いので、今回のような「多くの人を巻き込む」タイプの仕事に苦手意識があったんです。でも、進めるうちに感じたのは、様々な人の力を頼りながら取り組みを昇華させていく面白さ。私にない専門分野の知見を借りたり、私が気づいていない可能性を指摘してもらったりという経験をするうちに、自分ひとりで抱え込まずに仲間を巻き込むことを意識するようになりましたね。例えば、著作権管理の新フローでは、チェック業務を一部自動化するツールを導入。私一人では難しかった仕組みが実現できたのも良かったです。
早川:私も�向後さんの感覚に近いですね。前職時代の私はいわゆる“一匹狼”で、自分が良いと信じたことなら、自分ひとりの力技で実現しようとするタイプでした。ただ、今回のプロジェクトのような規模の取り組みは、一人の力では何ともならない。だからこそ、グループ内外のステークホルダーのみなさんが納得してくれるように、私たちが目指す世界観やビジョンを示し、仲間になってもらうというチャレンジの機会になったと思います。また、そうやって周囲に働きかけたからこそ、関係組織でもフローの見直しやアップデートを行う動きが広がっており、個人や組織に閉じず取り組みを発信することの意義を感じました。
上原:私たちが今回一番こだわったことは、「周囲を適切に巻き込む」こと。『スタディサプリ』のコンテンツは社内外の様々な立場の人々が関わって生まれています。中にはドラスティックに変えなければならないものもありましたが、私たちもパートナーもみんなにとって良いねと思える形で着地したかった。だからこそ、周囲と密にコミュニケーションを取りながら協力して進めていくことも大事でしたし、協働の質を高める上では相手の理解の解像度をこれまで以上に高めることも必要でした。そうした努力がピタリとはまり、一人ひとりが個性を発揮しながらも、全体として美しく調和のとれた仕事ができたことに、手応えを感じています。
Q:最後に、今後みなさんが実現したいことを教えてください。
早川:『スタディサプリ』がビジョンに掲げている、教育格差の解消を実現することですね。この10年超で一定の貢献��ができている部分もある一方で、社会を見渡せばまだまだ課題はある。特に学校によっては、先生方が生徒に対してしっかりと向き合えず悩んでいるケースもあると感じています。そうした教育現場の悩みをフォローするようなコンテンツやプロダクトを届けていきたいです。
向後:先ほど上原さんが述べていたように、今回のプロジェクトで整備したフローを土台にしながら、より良いコンテンツづくりに励んでいきたいです。教科書に取り上げられた文章や試験の問題文に書かれていたことの中には、社会人になった今でも覚えているフレーズや教訓のようなものがありませんか。私はそうした学びを『スタディサプリ』で届けたい。生徒たちの記憶に残るようなコンテンツをたくさん届けることが目標です。
上原:教材という「ものづくり」をキャリアの軸にしてきた私にとって、今回は「仕組みづくり」という意味で珍しい経験でした。不安もゼロではなかったけれど、実際にやってみたらこれまでのスキルを活かしながら楽しめた。だからこそ、私が本当にやりたいことは「ものづくり」に限らないのではないか、という発見がありました。そこで、自分の可能性を広げる意味で、オペレーションデザインやツール開発にチャレンジするのも選択肢の一つかもしれない。そうした幅広いキャリアを模索してみることも『スタディサプリ』の環境なら実現できるはずだと思っています。
記事中で紹介した事業(名称や内容含む)や人物及び肩書については取材当時のものであり、現時点で異なる可能性�がございます。